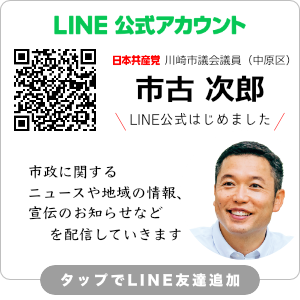決算審査特別委員会③ 気象防災アドバイザーの配置を!
※正式な議事録ではありません。
2款3項1目危機管理対策費のうち、雨量・水位情報提供業務委託料、及び防災気象情報提供業務委託料について伺います。
設問1
それぞれの業務内容、目的を伺います。
答弁1
「雨量・水位情報提供業務委託」及び「防災気象情報提供業務委託」についての御質問でございますが、「雨量・水位情報提供業務委託」の業務内容につきましては、雨量、水位、潮位及び気象に関する情報を観測するシステムを構築し、本市が運用している防災に関する各システムに観測データを捌共して有効活用を図ることを目的として実施しております。次に、「防災気象情報提供業務委託」の業務内容につきましては、防災気象コンサルティング業務、防災気象情報及び防災対策支援情報の提供、「川崎市防災気象情報」ウエブサイトの運用、水位監視カメラの運用等を実施し、災害発生時の気象状況等を共有して災害応急対策を円滑に行うことを目的として実施しております。
川崎市防災気象情報https://kawasaki.tenki.ne.jp/#/top/graphical
設問2
地域防災計画第3部第6章「災害情報の収集と伝達」では建設緑政局河川課、港湾局、上下水道局が雨量・水位・潮位テレメータ無線観測局の情報を収集するとありますが「川崎市防災気象情報」ウエブサイトの運営に関しての庁内連携について伺います。
答弁2
「川崎市防災気象情報」ウエブサイトにっいての御質問でございますが、
本市におきましでは、同サイトを通じて、災害時に必要な防災気象情報を全庁に共有しておりまして、各局それぞれ災害対応に必要となる情報を選択しながら活用しているところでございます。
令和3年度の「川崎市防災気象情報」ウエブサイトの再構築に当たりましては、建設緑政局と上下水道局それぞれが管理するカメラ等の公開ページを統合するなど、当該局と調整を行い、取組を進めたところでございまして、今後も関係局と連携しながら、運用してまいります。
設問3
上下水道局に確認をしましたら、防災気象情報は市内の雨量を確認する際に活用しているとのことです。排水樋管ゲート操作のマニュアルにも貴重な情報源として示されておりますので、今後も関係局と連携を図り、必要な改善があれば取り組んでいただければと思います。
次に市民の皆さんへの情報提供の観点からお聞きします。「川崎市防災情報」は「防災ポータルサイト」にリンクしていますが、「防災ポータルサイト」のアクセス数の推移等は確認を行っているのでしょうか。例えば、9月11日の集中豪雨時にはアクセス数が伸びている等、市民に取って、いざという時の情報を取得する手段となっているのか伺います。
また、「川崎市防災気象情報」ウエブサイトの使い勝手等について、市民の声を聞く機会を設けているのでしょうか?伺います。
防災ポータルサイトhttps://portal.kikikanri.city.kawasaki.jp
答弁3
「防災ポータルサイト」等についての御質問でございますが、
「防災ポータルサイト」は、本市の防災情報を集約し、緊急情報、避難指示等発令情報、避難所の開設情報等を、適切に市民に伝達することを目的としております。
平時の閲覧数につきましては、 1日当たり約500から1,000回前後で推移しておりますが、令和7年9月11日の大雨の際には、 1日当たり約56,000回と、大雨の影響を心配する多くの市民の方々から利用いただいており、今後も継続的にアクセス数を確認してまいります。
また、「川崎市防災気象情報」ウェブサイトは、操作方法等について市ホームページで御案内しており、危機管理本部に問い合わせが月に数回程度寄せられ、その内容は、主に過去情報の閲覧方法に関するものが多いものとなっておりますが、今後、市民向けの防災関連のイベントなどにおいて、「川崎市防災気象情報」ウェブサイトや「防災アプリ」等の普及啓洗又を行う予定でございますので、そうした際に、多くの方々から御意見を伺ってまいりたいと考えております。
設問4
アクセス数の推移をお聞きしますと、市民の方にとって貴重な防災情報の一つとなっていることが確認できました。ぜひ、多くの市民からの意見を聞き、ブラッシュアップを図っていただければと思います。雨量・水位情報提供業務委託について令和2年3月以降に直営だった通信網を含む気象観測システムをクラウド化したとお聞きしました。クラウド化したことによってのメリット、デメリットを伺います。
答弁4
「雨量水位情報提供業務委託」についての御質問でございますが、
令和2年3月から事業者の捌共するクラウド型の気象観測システムを利用することで、サーバーの維持管理や機器の点検、保守等を一括して委託することが可能となり、職員による運用の負荷を低減できていることがメリットとして挙げられます。
また、設備等が事業者の保有物であり、直接の管理ができないことによる不具合が生じないよう、月一回程度の事業者との連絡調整を行いながら、設備及びサービスの安定稼働を確認しているところでございます。
設問5
市民、庁内に貴重な防災情報を提供する設備に市の直接の管理が行き届かないというのは、大きなデメリットだと思います。今後も当事業については注視し、直営に戻すことも含め議論させていただければと思います。
異常気象による急激な天候の変化により想定を超える雨量が発生し、現在も深刻な浸水被害が発生しています。気象庁は所定の研修を受けた気象予報士等が予報の解説から避難の判断までを一貫して扱える気象防災のスペシャリストとして「気象防災アドバイザー」配置の取組を進めています。本市の防災気象情報の更なる有効活用の為にも「気象防災アドバイザー」配置の取組は有効と考えます。見解を伺います。
気象防災アドバイザーhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/gyomu/wxad/index.html
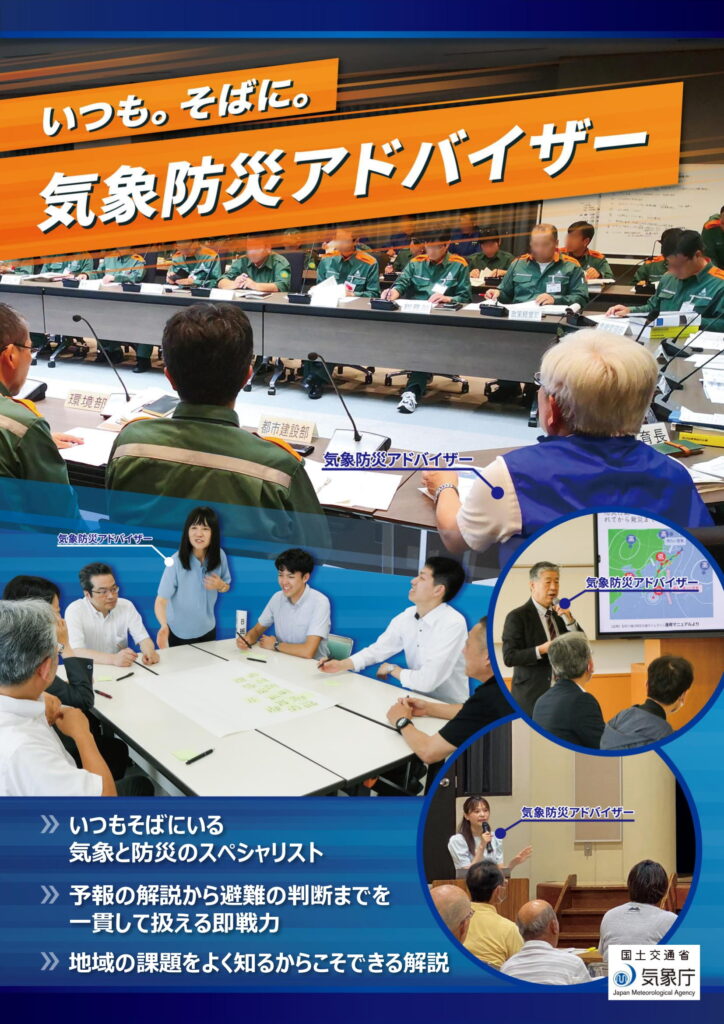

答弁5
気象防災アドバイザーについての御質問でございます
本市におきましては、横浜地方気象台及び日本気象株式会社から降雨予測や雨の降り方、気象警報の可能性など気象情報の助言を受けておりまして、これらの情報を基に大雨等への対応を行っているところです。
また、本年5月に実施した風水害図上訓練においては、横浜地方気象台から気象専門官を迎え、気象情報の取り扱いや、避難情報発信のポイントについて助言をいただくなど、職員の防災力向上に取り組んでおり、気象の専門家との連携を図っております。
今後も気候変動による風水害の増加も考えられることから、大型台風や急激な天候の変化に備えて、引き続き気象防災の有識者との連携を図ってまいります。
要望
気象予報士の方と意見交換した際、川崎市は鶴見川と多摩川に挟まれた水害リスクの高い政令市というお話がありました。気象庁の資料によると気象防災アドバイザーを自治体で任用することのメリットは地域の課題、地形等を踏まえた的確な助言を実施できると謳われておりますので、連携だけでなく、地域密着の気象防災の有識者の確保についても継続して調査、研究を行っていただくことを要望して質問を終わります。