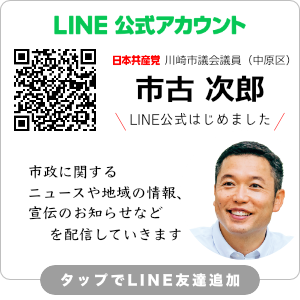代表質問(抜粋)最後の意見

最後に意見を述べます。
今回の質疑において、「国が」「国に」と国へ責任を転嫁する答弁が繰り返されました。地方自治体の役割とは何でしょうか。例えば、今回の代表質問でも多くの議論が交わされた「小児医療費助成制度」の歴史を振り返ると、1961年に岩手県和賀郡沢内村で乳児医療費助成制度としてスタートします。1957年には、村内の乳児死亡率が1000人あたり69.6人に達していましたが、制度実施後の62年には死亡率が0人となりました。それを契機に、岩手県、青森県、福島県において制度の導入が始まり、全国に広がっていくことになります。つまり、小児医療費助成制度は地域の子どもたちの命と健康を守るための地方単独のボトムアップ事業なのです。
そういった背景を鑑みず、市民からの繰り返しの要望に一向に答えようとせず、「国が一律に実施するもの」という考えを繰り返し、横浜が拡充の方針を固め県内ワーストとなったところで、ようやく拡充を表明しても、発せられた言葉は「苦渋の選択」です。国がやらない。思い通りならないから仕方なく拡充に踏み切った市長の姿勢は、地方自治体の責務である「住民福祉の増進」をあまりにも軽視した姿勢と言わざるをえません。
ぜん息を苦しんでいる高校生がいます。その保護者からは、小児ぜん息医療費支給事業の経過措置が3月で終了するため、受診回数を減らすことを考えているとの声が寄せられています。9月からの小児医療費助成の拡充を予定しているのであれば、途切れのない医療提供をと5カ月間の措置延長を要望しても「予定通り終了する」という、こども未来局長の冷たい答弁がありました。5か月の経過措置に必要な予算は概算で約2000万円。一方で、特別市を推進するための今年度予算は約2400万円に上るとのことです。なぜ、さまざまな課題に対し具体的な対応策を示さない特別市には予算を捻出するのに、ぜん息で苦しむ子どもたちへ、たった5ヶ月の延長にさえ、ゼロ回答なのでしょうか。改めて、小児ぜん息医療費支給事業の経過措置延長を強く要望します。
小児医療費助成の18歳までの拡充により、37年間にわたる市民からの要望の一つがようやく帰結することとなります。しかし、市民の声が止むことはありません。広がり続ける多摩川格差、高齢者や障がい者世帯へのエアコン設置補助、ひとり親家庭や中小企業、医療機関への支援など、物価高騰で苦しむ市民からの暮らしの声に、暮らしを守る要請に真摯に向き合い、川崎市が地方自治体としてのあるべき姿を取り戻すことを強く、切に要望し、質問を終わります。